「こんなことを、だね」 彼女は足を組みながら言った。 「している場合ではないと思うのは、私の思い違いかね、君?」 「思い違いではないと思いますよ。チェック」 「君の手は何時も詰めが甘い」 細くて長い指がナイトを動かす。 「そうですか? チェック」 そのナイトを僕のクイーンがなぎ倒した。 「君の問題点を挙げるとするならば、だね」 「はい」 「目の前の問題にだけ気をとられて、本当に大切な所に気づかない処だね」 「そうですか? これでも、注意深い人間で世間では通ってるんですけど」 「世間とは何だね? それは君自身ではないかね?」 「人間失格、ですか?」 「ほぉ、流石だね」 「お褒めに預かり光栄です」 僕は胸に手を当てて、一礼をしてみた。 彼女はふんっと、形のいい鼻を鳴らした。 「お気に召しません?」 「慇懃無礼な態度は好きではないのだよ。褒められたなどと、君は思っていないだろう? 太宰治なんて、君の中では常識の範疇。常識を褒められて喜ぶのは愚かしいだろうに。 さて、話を戻そう。君と話していると本筋から離れてしまっていけないな」 僕はそれを聞いて少し微笑んだ。 その言葉を、僕と話していると話が弾むと言っているのだと受け取って、何がいけないのだろうか? 「君の問題点は注意力が足りない、其れではないのだよ。一点集中型、というのかな? 一つのことに夢中になってしまって、余所が疎かになる。此れは由々しき事だよ、君」 そして、彼女の細くて長い指がルークを持上げる。 「君は私のキングの周りにだけ注意を払っていただろう? 確かに私は一見すると君に追い詰められていたように見えたかも知れない。しかしながら、」 そして彼女は、そのルークを盤上に戻した。 「チェック」 そういって、その指先をこちらに向けた。 「……」 僕は盤上を睨んだ。ああ、確かに。 「私の兵力は着実に君を追い詰めていたのだよ」 彼女は薄い、赤い唇で微笑んだ。 「さぁ、どうする?」 どうするもこうするも、この状態で僕が出来ることはただ一つしかない。両手を挙げて降参すること。 彼女は更に満足そうに微笑んで、足を組替えた。長い黒いドレスのレースの中から、黒い華奢なミュールが見えた。 「さて、話の続きだが、君はこのように一点集中型だ。だが、時々君は一点集中型を装っている時がある。君は蔑ろにしてはいけないものまで、蔑ろにしているだろう?」 彼女は豪華な椅子に身を沈めて、長い爪に塗られた紅いエナメルの様子を眺めながら言った。 僕は同じような豪華な椅子に座り、チェス台越しに彼女を見つめていた。 「さっきも言ったが、君はこんな事をしている場合ではないだろう? まぁ、チェスに誘ったのは私だから私にも非はあるとしても、だ」 「そうですね、実はこんな事をしている場合ではありません」 だが本当にそうだろうか? 彼女と過ごす時間がこんな事ならば、その他の事柄は取るに足らない事象に過ぎないだろう。そんなことを口にしたりはしないが。 「君は大学生だ、この事に依存は無いな?」 「ありませんね。実際に僕は大学生です。一般的な価値観からしてみれば」 「ただなんとなくなった、ということにしろ、君が大学生だという事実は消えないのだよ。そうだろう? ××大学英文科三年、 僕は黙って微笑んだ。内心では、彼女が僕の名前を呼んだことに喜んでいた。 「さて、今は1月の頭だ。此れも異存は無いな?」 「勿論です。暦にけちをつける馬鹿ではありませんよ」 「そして、1月10日から、君、試験だと言っていなかったか?」 「言ってましたね」 「君は大学生である。一週間もしないうちに試験がやってくる。君、こんなところに来て私とチェスをしている暇があったら勉強したらどうかね? 本業を疎かにするのは愚か者がする事だ」 僕は微笑んで、立ち上がると、チェス台の上に片手をつき身を乗り出した。 ビショップが床に転がり落ちる。 彼女の視線は一瞬そのビショップを辿り、すぐに僕に戻された。黒い瞳と長い睫が睨むようにして僕を見る。 「お言葉ですが、僕はこちらが本業だと思っているんですよ?」 そう言って相変わらずこちらを睨んでいる彼女の右手をとると、その甲に口付けた。 彼女は身動き一つしない。 「僕はこちらが本業だと思っているんです」 手を掴んだまま僕はもう一度、子どもに言い聞かせるように言う。 「此方? 此方とは何処だね?」 「貴女も人が悪いですね、ミス・ホームズ」 「ホームズは嫌いだ、と何度言えば気が済むのかね?」 「失礼しました。ミス・クイーン」 彼女は少し満足そうに口元を緩めた。 ミス・クイーン。 彼女が好きなエラリー・クイーンのクイーンの意味と、そのままずばり妃の意味がこめられている、僕だけが呼ぶ彼女への渾名。 「ミス・クイーン、貴女の助手が僕の本業だと僕は認識しているんですよ。そんな冷たい態度は酷いじゃないですか」 彼女はしばらく僕を黙って見つめ、やがて一度瞳を閉じる。ゆっくりと瞳をあけ、それと同じようにゆっくりとした動作で右手動かす。 僕は大人しくその右手を解放した。 彼女は自由になった右手で僕の頬を軽く撫でて、また膝の上に戻した。 「確かに、今のは酷かったかもしれない。謝るよ。だがね、君。私の助手が大学で悪い成績をとったなんて恥だろう。世間に顔向けできない」 「世間とはなんですか?」 「私自身だよ。私のこの、取るに足りないプライドが許さないのだよ」 彼女は悠然と微笑んだ。 ここまで言われて反抗できなかった。 「わかりました。でしたら、貴女の助手に相応しい立派な成績をとるために勉強してきます」 「そうしてくれたまえ」 「しばらくは来ないと思いますが」 「構わないよ。その間は仕事を断るから」 「いつも断ってばかりじゃないですか」 「私の食指が動かないんだ」 「まったく」 僕は最近巷で少し、業界内ではとても、噂になっている探偵の女王を見つめた。 3年前に亡くなった彼女の夫の死に隠された本当の意味を知るために、彼女は探偵になったという。名家のお嬢様であった彼女は、働かなくても生きていける。だから、本当に彼女の夫の死に関連ありそうな事件や気に入った依頼人の事件しか引き受けない。 そんな彼女に事件を引き受けてもらった僕は、やはり彼女に気に入られているのだろうと、傲慢かもしれないが思う。 「そういえば、林さんはどうしたんですか? 今日は姿が見えませんけど」 「林? 買い物だよ、そろそろ帰ってくると思うが」 常に黒い衣装に身を包んだ中世の貴婦人のようなこの未亡人は、大きな屋敷に執事と二人ですんでいる。 僕はたびたびここに訪れて、いつからか彼女の仕事の助手をはじめた。 助手? まぁ、大体助手みたいなことを。大抵は彼女のチェスの相手だけど。 僕はゆっくりと、チェス台の上から手をどかし、姿勢正す。 「今、引き受けている事件は?」 「事件? ……嗚呼、あれか。死ぬ前日に恋人が送ってきたメィルの内容か」 「そうです。あの暗号は?」 「解いたよ。昨日のうちに依頼人にメィルで報告しておいた」 「なんだったんですか?」 「別に……。取るに足りない恋人達の睦言だよ」 彼女は僕から視線を逸らした。 陶器の人形のような顔が一瞬だけ、歪んだ。亡くなった彼女の旦那を思い出しているのだろう。 僕は彼女の旦那について、警察のエリートだったということしか知らない。名前も知らない。顔も知らない。 でも、彼女が本気で彼を愛していたことだけは知っている。 働いたことなど無いお嬢様が、探偵なんて初めたのだから。影ではお嬢様のごっこ遊びだと陰口を叩かれながらも、必死に真相を探ろうとしているのだから。 彼女は、本気で愛していた。 違う、愛している。 「……なら、いいですね。帰ります」 僕は居た堪れなくてそう告げた。 「そうか」 彼女はそういって立ち上がった。立ち上がった彼女はもう、いつもの彼女だった。 彼女が玄関に向かって歩き出す。 大きな階段をゆっくりとおりる、彼女の後ろをついていく。 こつ、こつ、と足音を響かせて。スカートをなびかせて。 僕はこの、不思議なクイーンを愛している。 人形のように美しい彼女を愛している。 僕はきっと、永遠に彼女の夫には勝てない。 死んだ人間には勝てない。 ならばせめて、いつまでも彼女の夫の真相がとけなければいいのに、と思っている。 そうすれば、きっと何時までもそばにいられるから。 彼女は大きな玄関の扉を開けた。 「では、今日もつき合わせてすまなかった。そういえば、お茶も出していなかったな……」 「いいえ。好きでやっていることですから。それに林さんがいないのならばしょうがないでしょう」 一度チェスを始めた彼女がお茶を出すなんて気の利いたことを思いつくわけがない。彼女だって十分に、一点集中型だ。 「失礼だな。林がいなくてもお茶ぐらい私でも淹れられる。あまり侮るな」 彼女はそう言って不機嫌そうに眉をひそめた。そういう意味で言ったのではない、と僕は弁解しかけてやめた。意味のないことだ。 「侮ってはいませんよ。ミス・クイーンにお茶を淹れて頂くなんてそんな……」 僕はそう言って微笑んだ。 「そんな、なんだね?」 「図々しいことは出来ません」 彼女はふんっと笑った。 確かに彼女はお茶ぐらい淹れられる。簡単な料理なら出来る。でも恐ろしく手際が悪い上に、お世辞にも美味しいとは言えないものだ。ただ、掃除と洗濯は得意らしい。あくまでも本人の主観によるものであり、僕は見たことがない。客観的な判断が出来る唯一の人物、林さんとはあいにく僕は彼女を通してではないと意思の疎通がとれない。 「  」 」突然、彼女がそう言った。彼女は言ってから視線を庭に向けた。 沢山のオールドローズ。その薔薇の道を一人の老人が歩いてくる。 「  」 」「  」 」「ええっと、  」 」僕が答えると、林さんだけではなく、彼女も少し嬉しそうに笑った。 「 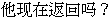 」 」「  」 」「 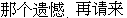 」 」林さんが僕の方を向いて言うのに、僕は曖昧に微笑んだ。残念ながら僕は中国語がわからない。 「また来るように、と」 察したのか、彼女が代弁してくれた。 「では、また。きちんとテスト勉強するように」 「はい」 僕は片手を挙げて屋敷からでた。 背後で扉が閉まる音が聞こえた。 庭には沢山のオールドローズ。 その中を歩いていく。 「 彼女の名前。 薔薇の名を持つ彼女は、薔薇と同じだ。綺麗で凛としていて、そして棘がある。自分を守るために。 僕は今まで一度も彼女の名前を呼んだことがない。だから僕は彼女をミス・クイーンと呼ぶ。 彼女がクイーンならば、僕は所詮ナイトだろう。ポーン3つ分の、キングとでは相手をチェックメイトできない小駒。 僕は中国語は話せないから、助手を気取っているくせに執事とは話が出来ないし、エラリー・クイーンを読んだことはない。僕はホームズが好きなんだ。 この距離感は拭えない。 軽くため息をつき、薔薇の屋敷を後にした。 |
▽